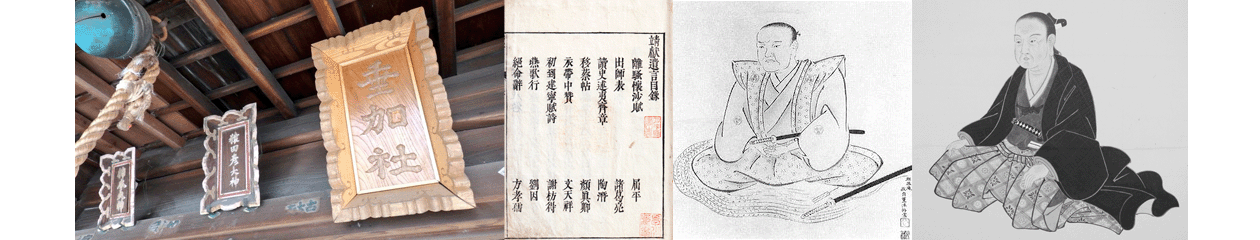文天祥は言わずと知れた南宋の忠臣で、字を宗瑞といいます。南宋の第七代皇帝である恭宗の時代(元号が徳祐なので、恭帝を徳祐帝と称す)に元軍は長江を渡って東に下り、首都の臨安(現在の南京)に迫りました。かくして天下に勤王の詔が発せられましたが、宋の重臣や将軍たちは元軍に恐れおののくばかりでした。
ときに文天祥は三十九歳、贛州(江西省南部に位置する)の知事を務めておりました。彼は吉州(現在の江西省吉安市)の出身で、弱冠二十歳で科挙に首席合格した秀才であり、高級官僚として裕福な生活を送っておりましたが、いまこそ国恩に報いる秋と意を決し、家財を全て売り払い、僅かの手勢を率いて臨安に赴きました。これを見た天祥の友人は、「群羊を駆って猛虎を手打ちにするようなものだ」と言って彼を引き留めようとしましたが、天祥は、「宋室三百年の恩義にもかかわらず、天子の詔に応じる臣民の一人とてない今こそ、拙者が一身を投げ打つことによって、天下の忠臣義士に蹶起を促すのだ」と言って聞き入れませんでした。
かくして天祥が臨安に到着したとき、宋の各地は次々と元軍に占領され敵に降参する者が後を絶ちませんでした。天祥はあくまで徹底抗戦を主張しましたが、右丞相(宰相)の陳宜中はその策を聞き入れなかったばかりか、かえって五代皇帝理宗の后である太皇太后に進言して元軍に使者を派遣し、国璽を渡して降伏を申し入れてしまいました。この国璽は、我が国で云う処の三種の神器のようなもので、皇位の御印ですから、それを敵に渡すという事はすなわち国家の滅亡を意味します。
この降伏の申し出に対し、敵将伯顔(バヤン)は、宰相の陳宜中が直接来るよう求めましたが、彼はすでに遁れ去っていたため、太皇太后は、急遽天祥を右丞相兼枢密使に任じ、天祥は官位を辞退しながらも、使者として元軍に赴きました。伯顔は天祥が当然に降参を申し入れに来ると思っていたので、彼が元に対して不屈の態度を示し、大臣職の提案も言下に拒絶するのを見て怒り、そのまま身柄を拘束して元の都がある大都に北送(北に護送するの意)しました。そして臨安に入城すると、恭帝と太皇太后、皇太后もまた北に連れ去りました。
二王を新帝に奉じる
しかし、幸いにも、五代皇帝度宗の子で徳祐帝の兄弟にあたる益王昰と衛王ヘイ(日の下に丙)の二王が浙東に留まっておられたので、天祥はこの二王を奉戴して宋朝を恢復せんとし、北送の途中の鎮江で脱走することに成功しました。天祥は飢えを忍びながら辛うじて元軍の追跡を逃れ、二王の行方を求め、ついに福州において帝位に就いていた益王昰、すなわち第八代端宗の下に参じ、枢密使や同都督、諸路軍馬といった軍司令官の職に任じて宗室の命運を委ねられたのでした。
天祥は天下の豪傑を糾合して勇敢に戦い、一時は数州県を取り戻して宋の軍勢もやや盛んとなりましたが、やがて興国(江西省内の地名)での戦に敗れ、空坑(不明)に退いたところで部下の兵が総崩れとなり、妻子・幕僚等みな元軍に捕らわれました。それでも天祥は屈せず、離散した味方を集めて再起を企てましたが、間もなく端宗が崩御し、群臣の多くは絶望して散り去ろうとしました。
そんななか、大臣の陸秀夫は、「まだ端宗の弟である衛王ヘイがいるではないか」といって、わずか八歳の衛王を新帝(その元号が祥興なので祥興帝と称す)に擁立して宋室の中興を図りました。天祥は、新帝に上表して、敗軍の将である自らの責任を弾劾しましたが、かえって少保・信国公に任じられました。少保は大保の副官で、天子を輔翼し、これを道に帰せしめるを任とし、信国公とは、天祥が信国に封じられたのでこう称します。また先に彼は、枢密使も拝命しておりましたので、絅斎は、巻頭において天祥を「宋の少保枢密使信国公」と称しているのです。
さて、祥興帝を奉じて力戦した天祥ですが、軍中で発生した疫病のせいで彼の母親や長男も病没し、天祥の家族係累は皆尽き果てました。さらに形勢は日を追うごとに悪化し、ついに天祥は敵の急襲に遭って再び捕らわれ、毒薬を飲んで死のうとしましたが死ねませんでした。天祥を引見した元将の張弘範は彼に拝跪を命じましたが、天祥はこれに屈せず、むしろ固く死を請うたのを許されず、船中に閉じ込められました。その後、厓山の戦いで宋は敗れ、前述した陸秀夫は、自らが擁立した幼帝、祥興帝を抱いて入水しました(一二七九)。かくして宋は名実ともに滅亡し、天祥らの抵抗は潰えたのであります。
張弘範は、戦勝の大祝賀会の席に天祥を引き出し、お前が元に仕えるならば宰相の地位を与えようといって、降参を勧めましたが、天祥は頑として聞き入れなかったため、その身柄を元の新たな都となった燕(現在の北京)に北送しました。北送の途中、故郷の吉州に差し掛かった天祥は痛恨し、生まれ育った盧陵で死のうと思い絶食しました。その際、天祥は祖先の墓に奉告文を捧げ、そのなかで「ああ、古より危乱の世、忠臣義士・孝子慈孫、その事の両全することあたはざるや久し。(古へより危乱の世にあっては、忠孝の心深い人物も、その両方を全うすることは極めて困難として来た。)」として忠孝の葛藤を述べつつも、「幽明死生、一理なり。父子祖孫、一気なり。冥漠知ることあらば、尚はくはこれを哀監せよ。(忠に徹すればそれはおのづから孝に徹したことになる。そも〳〵幽も明も、死も生も同じ道理が貫いてゐることであり、先祖と子孫の間も、同じ気が続いてゐるものである。父祖の神霊よ、知ることあるならば、何卒このわたくしの心を哀しみ鑑みたまへ。)」と記しています。これについて強斎は『講義』で、「つまる処、君の為に忠と云に死すれば詰るところ孝をうしなはぬ。畢竟忠義にはづかしふ無い様につかまつれば、忠孝二つないからは、孝にも失わぬ程に、又何怨むとあること。・・・此の身は先祖の忠義なりに遺し下された形見じやからは、先祖の神霊の御座りて此の度の大事を御存知なされたらば、此の段を御覧なされとあること明らかなことぞ。」と述べています。天祥は絶食して八日経っても死なず、盧陵を通り過ぎてしまったので自殺は思いとどまりました。前述したように、強斎その人も、天祥と同じくこの忠孝一致の問題に苦しみぬいた一人でした。彼は、父の願いであった仕官を拒み、困窮のなかで病床の父を満足に看護することもできず、さらには崎門の慣習によって養子を排したが故に血統を断絶せしめたことを生涯の遺恨とし、『自首文』のなかで自らを「不孝の刑人」と称してその罪を謝したのでした。そしてその最後に「過廬陵文山(廬陵を過ぐるの文山)」と記したのは、自らの心事を、天祥が故郷廬陵に至ったときのそれと重ね合わせたからにほかなりません。
元将との舌戦
かくして燕(北京)に到着した天祥を引見したのは、元の大臣博羅(ボロ)でありました。博羅は天祥が自分に対して軽く長揖(両手を組み合わせて上体を前方に傾け頭を下げる挨拶)するのみで拝跪(ひざまずくこと)しないことに怒り、先に天祥が太皇太后の使者として元に降伏を申し入れながら、北送の途中の鎮江で脱走した態度の矛盾を責めました。すると天祥は、己の利のために国を売る者は絶対に逃げ出さない、しかるに自分が逃げたのは、むしろ己の利のためではない証拠であり、度宗の御子である益王昰(し)と衛王ヘイをお輔けし、かつ母に孝養を尽くすためであったといって反論しました。
さらに博羅が、徳祐帝が存命であるにもかかわらず、前述した二王を推戴擁立したのは不忠だと言って責めると、かのときはまさに国家の非常時であり、そうしたなかでは、「社稷を重しとし、君を軽しとす」、すなわち君主個人の存否よりも国家の存続の方が大事だと述べ、むかし晋の洛陽が賊に陥った際、賊に降った懷帝や愍帝に従って北送されたものは忠臣ではなく、むしろ元帝に従って晋中興を計ったものこそ忠臣である、同様に、北宋の都、汴京が金に陥った際に、金に降った徽宗や欽宗に従って北送されたものは忠臣ではなく、高宗に従って宋中興を計ったものこそ忠臣であると答えました。
反駁に窮した博羅は、話題を転じ、元帝や高宗はいずれも先帝より命を受けているが、二王はそうではないから簒奪ではないかと問うと、天祥は、二王はともに度宗の子で、徳祐帝の兄弟であるから宋室の正統であり、ともに徳祐帝が退位された後(国璽を元に渡した時点で退位したも同然ということか)に即位しているので簒奪にはならない、また二王が宮城を脱したのは、太皇太后の命であるから、命を受けていないとはいえないと述べ、博羅を論破しました。また国家の命運が尽きても、大病にかかった親を子がなんとか救おうと努力するように、我が心一杯の忠義を尽くすのが臣下の務めであるとも述べ、博羅に死を請うたのでした。かくして博羅は天祥を殺そうとしましたが、元主フビライがこれを許さなかったため、天祥は牢獄に幽閉されることになりました。この獄中において天祥が賦した詩が、世に有名な『正気の歌』です。
『正気歌』
「正気」とは孟子のいう「浩然の気」のことで、強斎によると、「天地の間すべて理と云ふより外なうて、此理なりにどこ迄もやまず行はるヽ所は皆気の流行で、古今一体、不変不動」のものであり「さて又人で云へば、子として孝、臣としては忠と云ふ当然の義理より外はなうて、其の義理のどこまでもやまず、何やうなことにも屈せず、忠孝と云ふ理なりに行はれてゆく、そこが正気ぞ」ということです(『講義』)。天祥は、この『正気歌』の序文において、暗く狭い土牢の中に起居すること二年、夏には蒸し暑く、腐った穀物や鼠の死骸、囚人たちの汚物の悪臭が充満し、穢気に犯されながらも病気にならなかったのは、平素からこの正気を養ってきた結果であると述べています。
入獄から四年の後、フビライは天祥に対し、彼がかつて宋に仕えた態度で元にも仕えるならば、大臣の位を与えようと申し出ましたが、天祥は他国の君主に仕えるつもりはなく、ただ一死を請うのみであると答えたため、ついにフビライは天祥を元都の柴市において処刑しました。(一二八二)。享年四十七歳でした。
さて、そんな天祥の遺言として絅斎が掲げたのが『衣帯の中の賛』です。これは天祥が身に着けていた帯の内側に書いたのが死後見つかったもので、賛とは、人物・文章・書画等を讃美するところから起こった文体のことです。それは次のようなものです。「孔、仁を成すといひ、孟、義を取るといふ。それただ義盡く、仁至る所以。聖賢の書を讀み、學ぶ所何事ぞ。而今にして後、庶幾はくは愧づることなからん。」これは孔子が『論語』のなかで「身を殺して仁を成す」と言い、また孟子が「生を捨てて義を取る」と言った二言を受けたものですが、その意味について絅斎は「仁と義と二つかと云へばそうでない、義の尽くるところが仁の至ると云処。・・・義さへ一ぱいにしつめると、吾が心はをのづからをちつき安んずる、其の安んずるまでをしおヽせることぞ」と述べ、平生正気を養った天祥の、死に臨んで安らかな心境を表したものです。天祥の死後、妻の欧陽氏はその屍を収め、義士の張千載はその遺骨を背負って郷里の吉州に葬りましたが、奇しくも同じ日、先に死んだ天祥の母の柩が吉州に到着したので、人々はこれを見て忠孝の誠が感応したのだと言ったそうです。
「社稷を重しとし、君を軽しとす」
さて、これまで『遺言』が描く文天祥の生涯を見てきましたが、そのなかには、我が国の歴史にも通用する重要な論点が含まれていると思います。それは、元将博羅の詰問に対して、天祥が喝破した「社稷を重しとし、君を軽しとす」という言葉の意味についてです。上述したように、これは徳祐帝が北送された後に、天祥が残された二王を天子に奉じたのは不忠ではないかという博羅の問いに答えたものであり、天祥は続けて、むかし晋の洛陽が陥った際に、敵に降った懷帝と愍帝に従ったものは忠ではなく、逆に抗戦を続けた元帝に従った者こそ忠であると述べましたが、このくだりについて絅斎は『講説』のなかで次のように述べています。「元帝に従う者にも心変わりはない者もあれども、日本でも後醍醐天皇の兵、山軍に負けさせたまい尊氏がいつわりて君にお恨みはござらぬ、とかく味方へ御入れあるようになされよと云うておこすを誠と思召されて余りまけさせ給いて、先ず一旦の計略に御入れある。そのときに義貞がうらみを申し上げたれば、先ず当座の計略なり。そのしるしには一宮に三種の神器を御ゆずりありて、義貞にこれを取りたてまいらせよと仰せつけられて、義貞は一宮をもりたてまつりてこの国へ落ちらるるとき左馬之助や宇都宮、土肥、得能、河野の一族どもはこの国へつき下る。とかくこの時は天皇につきまいらする者も、二心はいだかねどもこの時はみなみな思い思いになってどちへつきまいらするも奉公なれどもこの時に当たりては北国へつき下るはずなり。天皇降参なされたといえばもったいない故じやがまづ尊氏が呼びたてまつるにあめおめと御入れあればこれは伊弉諾伊邪那美以来の汚れをなし玉へり。すれば御正統は一宮へ伝わり三種の神器も伝わればもはや天下の主は一宮ゆえこの方へつきまいらするはずの故なり。この時は社稷重しとして君は軽しとする。先祖以来の天下を人に遣りて降参するような腰抜け。先祖へ対して不忠ものそうしたときは先祖社稷へ対して仇なれば討殺して苦しうない。」また強斎も『講義』において、次のように述べています。「後醍醐帝の高氏と和睦のとき天皇に従って高氏方に附いたものは不義の賊臣、大義を知らぬからぞ。義貞に従って宮の御供をしたものは忠ぞ。大義と云うはこの様な処で見たがよい。大義が明らかになひと君の降参なされたからはと云てともに降参して国を亡ぼすも知らぬぞ。どふなりともして社稷を存するやうに、其の天下を他の手に渡さぬやうにするが忠義の大筋目と云うもの。」
この絅斎と強斎の態度は、先に諸葛亮の巻で、劉備の子劉禅が蜀に璽綬を奉じて投降したことについて、劉禅を足利尊氏に降参した後醍醐天皇になぞらえ、その君主としての不徳を厳しく批判したのと同じです。しかし一方で、崎門学は「君君たらずとも、臣臣たらざるべからず」とする『拘幽操』の精神を要諦とするのですから、これと「社稷を重しとし、君を軽し」とする天祥の態度は一見すると矛盾するように思われます。したがって、この二つの命題をいかに止揚し、整合的に理解するかという事が問題になります。
重要なのは、天祥が博羅に反駁したように、天祥の奉じた二帝のうち、まず端宗は徳祐帝が元の伯顔に国璽を捧呈して退位されたあとに即位し、また次の祥興帝も端宗が崩御されたあとに即位されたという点です。たしかに、徳祐帝が伯顔に拉致し北送されたとしても、帝が位に在る限り、新帝の擁立は簒奪になるでしょう。しかし帝が退位や崩御によって位を去られた後であれば、宋室の正統を継ぐ二王が新帝に即位したとしても何ら問題はありません。あるいは逆の言い方をすれば、帝が位に在る限り、たとえその帝が敵国に拉致され、奸臣の傀儡であったとしても、かりそめにもそれが天子の命である以上は、臣下たるもの絶対に従わねばならないということです。奸臣曹操、献帝の命を竊むといえども、劉備は漢の正統であるにもかかわらず、曹丕が献帝を害し、帝位を簒奪したと聞くまでは、いやしくも帝位に就かず、臣下の分を守ったのはそのためです。また上で見た後醍醐天皇の故事についていえば、高氏に降った後醍醐帝ではなく、北国に下った一宮に従った義貞が忠臣といえるのは、後醍醐天皇が皇位の御徴である三種の神器を一宮にお譲り遊ばされ、御位を禅譲されたからです。もし一宮に三種の神器がなければ、高氏、帝の命を竊むといえども、あくまで正統な君主は後醍醐帝であり、天下の諸侯は抗するを得なかったでしょう。
余談ながら、土佐崎門派の谷秦山は山崎闇斎の末弟で『保建大記打聞』を著した崎門学の重鎮ですが、その玄孫(孫の孫)の谷干城は、西南戦争のとき熊本鎮台の司令官を務め、西郷軍の猛攻から熊本城を死守しました。これがもとで戦況は逆転し、西郷軍は鹿児島への後退を余儀なくされます。無論、干城とて、大西郷に対するシンパシーや明治政府に対する不満がなかったとも限りません。しかしそれでも彼が飽くまで西郷軍の通過を許さなかったのは、たとえ政府が失政を働くとも、かりそめにもそれが天子の命を拝する以上は、断じてこれに従わねばならないという臣下の分を弁えていたからであり、それこそまさに干城が受け継いだ崎門学の精神に他なりませんでした。対して昭和に至り、「昭和維新」を叫ぶ青年将校は政府転覆による国家改造を企て、君側の奸たる元老重臣たちの誅殺を図りました。たしかに彼らの動機は「汨羅の淵に波騒ぐ、・・・社稷を思う心なし」とうたう憂国の至情に発するものであったことは疑いありませんが、たとえ奸臣とはいえ、かりそめにも陛下の大命を受けた「股肱の臣」を誅殺することが、たとえそれが「社稷を思う心」に発する純粋な行動であったとしても、義ありや否やという点については、これまで述べた崎門の立場からいささかの疑念を拭えません。
では、奸臣どものなすがままかといえば、そうでもないのです。天祥について云えば、彼は開慶元年、二十四歳のとき、宦官の董宋臣が大事に当たっては首都臨安は守りがたいと言って遷都を主張したので、董を斬って人心を一にし、もって国家を安んずべきであると上書しました。また徳祐元年、四十歳のとき、呂師孟、国政を恣にして跋扈したので、またこれを斬って将士の気を奮起せしめられよと上書しました。しかし、「汨羅の淵」に身を投じた屈平も、主君の懷王とその子の襄王にしばしば諌奏したものの、自らを讒言誣告した上官大夫を奸臣として誅殺することはしませんでした。臣下として出来ることは、ただ義によって主君をお諫めし、君命にあらざれば、いやしくも出処進退しないということです。 これに関連して、近藤啓吾先生の記された『絅斎より強斎へ―わが思想遍歴のあとを省みる―』に大変重要なことが書かれておりますので、以下に引用します。
〈昭和二十年八月十五日の敗戦に、私は絶望し、喪心し、いかに活くるかの道を見失ひ、自決をも思つてゐた。そのやうなうちで、その年の十月、平泉寺に歸隱してをられた平泉先生をおたづねしたことが、私の崎門学修学の新しい出発となつた。私は先生に戦争終結への疑問を訴へ、むしろ陛下の戦争終結のご決意を、継続に翻意していただくべく、何故先生は身を挺せられずに、ここに隱れられたのであるかと、内心先生に反抗の姿勢があることを免れなかつた。私は西郷隆盛の挙兵をも例に挙げていおたづねしたのである。
黙つて私のいふところを聞いておられた先生は、「陛下はこの度の廣島に落とされた爆弾の惨状を聞しめされ、もうこれ以上悲惨な戦争を続けて、これ以上国民を苦しめることはできないと判断され、戦ひを止める決意をされたのである。もしこの際、陛下にそれをお止めする道がありとすれば、日本に直ちにそれに報復する、それ以上強力な用意がありますので、それによつて勝利に転ずることができます、と申し上げられることばのあつてのことでして、近藤さん、いまの日本にその兵器がありますか。それが無いのに、国民の為に戦ひを終へると判断された陛下のご決意をお翻へし願うことはできません。」「西郷の学問は禅であり陽明学であつて、その決意はそれから出てゐる。近藤さん、あなたは、今まで学んで来たことが少しも役に立たず、却つてそれを棄てるといふのですか。」「私は、マッカーサーが、陛下の御身柄をだう扱はんとしてゐるのかを憂へている。陛下の將来がはつきりした時、私は私の生涯をきめようと思つてゐる。近藤さんも、私と一しよに今少し生きて、陛下の御前途を見守つていただけませんか。」と語られた。
当時、先生の軍関係の門下のうちには、敗戦に承知できず行動を起こさんとし、その後援、乃至了解を先生に求めて来たものもあり、先生はその人々を抑へて、その志を暫らく黙々と持ち続けられるやうにと諭してをられたのであり、そのうちにはマッカーサー暗殺を計画してゐる人々もあつたと、それは後にうかがつたことである。先生の、あなたは今まで勉強して来たことが少しも役にたたず、却つてそれを棄てようとするのですかといふお諭しは、私の胸にこたへ、身ぶるいする思ひでうかがつたことであつたが、実はこの時、先生ご自身が、我国未曽有の大変に当つて、その意を確立する為めに、必死に闇斎・絅斎・秦山といふ崎門諸先学の教にすがつてをられたのである。・・・
私が、先生の戦争継続を、何故身をもつて陛下にお願ひ申し上げなつたのかといふことに疑問を持ち、否、反撥に近い気持を抱いてゐたことは既に述べた。私のこの気持の裏には、阿南大將の自決、宮城内事件を起した陸軍將校への同情が存してゐたのである。・・・
後日のことであるが、先生は谷干城將軍の熊本城死守について語られて、「大先輩である大西郷の率ゆる精英の大軍に対し、勅命によつてこの城を守る、勅許がなければ一兵といへどもここを通過することを許さぬ、いはれて城を守り通されたが、この決意は谷家の家学、そしてそれを導いた闇斎先生の教へによるものである」と讃辞を捧げられたが、この谷將軍の熊本城死守と西郷の挙兵とを比較することによつて、先生の私に対して歎ぜられた「今まで学んで来たことを全部棄てる」といふことの意味が初めて了解せられるのであるが、私がこの先生のお歎きの意味を解することができたのは、それよりずつと後のことである。〉