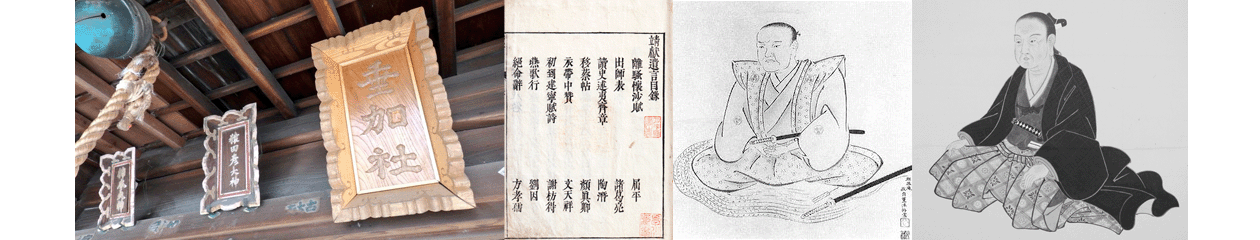顔真卿は字を清臣と云い、琅邪臨沂(現在の山東省臨沂県)に本籍を置く顔氏の出身です。この顔氏は、孔子の弟子として有名な顔回を輩出し、代々学者や能書家を輩出してきた名門であり、真卿もまたシナを代表する書の大家として知られています。唐の玄宗の治世に、平原(現在の山東省済南府平原県)の太守を務めていたとき、河北三道(平廬・范陽・河東)の節度使(辺境防衛の任に当たる)であった安禄山が反乱を起こし、真卿にも河北で官軍を防ぐよう命令してきましたが、真卿は都長安に使者を派遣して玄宗に禄山謀反の事を奏上し、禄山からの使者を見せしめに斬って賊軍との戦いに備えました。
当時、破竹の進撃を続ける禄山の軍勢に対して、河北諸国はことごく靡き従い、玄宗は「河北二十四郡にまったく忠義の士はいないのか」と落胆しておりましたので、真卿の上奏を聞いた玄宗は「朕は顔真卿がどんな様子をしているかを識らないのに、よくもこの様に忠義を尽くしてくれると」と言って大いに喜んだといいます。
同じ頃、真卿の従兄である顔杲卿は常山(現在の河北省正定府)の太守を務めておりましたが、杲卿もまた兵を起こして賊を討とうとしておりました。真卿は杲卿に使者を送り、河北から都長安への西進を続ける禄山の退路を遮断するよう連絡してきたので、杲卿は謀略を以て河北の要地である井陘口と饒陽にある敵を追い散らしたので、河北の十七郡はたちまち朝廷に帰し、禄山は長安に入る関門である潼関を攻めるのをやめて洛陽へ引き返しました。しかし、杲卿は兵を起こしてまだ日も浅く、守備の態勢が不十分であったため、禄山の賊将、史思明による突然の来襲によって常山は落城し、杲卿は捕らわれて身柄を洛陽にある禄山の下に送られました。禄山は、自分が天子に申し上げて杲卿を常山の太守にしてやったのに、杲卿が自分に従わないのは何故かと責めたのに対して、杲卿は、もともと営州(南満州の地)の羊飼いをしていた夷狄に過ぎなかった禄山を河北三道の節度使に任命した朝廷の厚恩に叛いて謀反を起こしたのは何故か。自分や禄山の禄位はみな唐のものであり、謀反を起こすのは国賊であると答えたので、禄山は激怒し、杲卿をなぶり殺しにし、それでも死ぬまで禄山を罵るのを止めなかったので、その舌を鉤で引き切り、顔氏の一族三十数人を皆殺しにしました。
常山の陥落によって後方の憂いがなくなった禄山は、ついに潼関を陥れて長安に迫り、玄宗は蜀に出奔します。これにより、玄宗の太子亨が帝位に就いて粛宗と号しました。絅斎は、この粛宗の即位を問題とし、『講義』で次のように述べています。「此時、玄宗蜀の国へにげられたる道にて、太子の供せられたるに言はるヽは、我は蜀へのく間、其方は跡に残りて天子の位に卽き敵をふせげと云置て行かれたり。其後群臣いづれも進めて位に御卽きなされよと云ふとき、終に位に卽かれたぞ。初めは事の外玄宗の前では辞退せられたれども、是にては遂に位に卽く。此事どふでも粛宗の誤ぞ。平生さへなるに、別して乱世の最中に親は流浪して走行くに、其跡にて推して位に卽けば、どうでも奪たになるぞ。尤も玄宗の言付とは云ひながら、粛宗何分にも辞退して申されたらば、何しに玄宗の無理やりには言はれぬはづぞ。下地はすきなり、御意は重し(もともと好きなところへ、他からも好意をもって勧められる。こんなに都合の良い話はないとうたとえ)と云ふ類にて、幸にせられたると疑がかヽる。それで此論あるぞ。其ならば天下の大将として下知は誰がせふぞと云へば、さればのことよ、固より天下は玄宗の天下也。粛宗は太子なれば、玄宗の名代として下知をするに誰か異義を云ひ手があろふぞ。こゝで粛宗が人欲に溺れて父子の義理を破られた、残多ことぞ。」(括弧内筆者)君命によらざる即位は、君臣の義に悖るという事です。
さても、粛宗は、真卿を工部尚書(公共工事を司る省の長官)兼御史大夫に任じ、また全国に恩赦の書状を発して各軍を督励したので、官軍次第に形勢を挽回し、長安と洛陽を回復して唐朝は再興するを得ました。かくして朝廷に復帰した真卿は、改めて御史大夫に任じられました。御史大夫とは、官吏の邪悪を糾察弾劾する目付役のことです。直言を憚らぬ真卿の態度によって百官は粛然として秩序を回復しましたが、それが故に李輔国や元載と云った時の権臣たちの忌むところとなり、真卿は幾度となく讒言誣告による左遷貶謫の憂き目に合いました。そして、ついに徳宗の治世に盧杞という人物が大臣になると、彼はますます真卿の剛直を憎み、徳宗に勧めて、汝州(河南省臨汝県)で謀反を起こした節度使、李希烈の宣慰(宥め従えること)に真卿を派遣せしめました。周囲は真卿の身の上を按じ、その汝州行を引き留めましたが、彼は君命に逆らうわけにはいかないといってそのまま出発しました。汝州に着くと、希烈は真卿を脅して降伏させようとしましたが、真卿はむしろ希烈の不義を責めて臆しませんでした。その内、希烈の部将周曽等が希烈を排して真卿を節度使に奉じる企てが発覚したため、希烈は同様の事態が起こることを避けるため、真卿を自らの本鎮(本籍地)である蔡州(現在の河南省汝南県)に移しました。この蔡州への移送に際し、真卿が自らの死を悟って記したのが、絅斎が真卿の遺言として掲げる『移蔡帖』です。以下に本文と近藤先生の正訳を掲げます。
「貞元元年正月五日、真卿、汝より蔡に移る、天なり、天の昭明、それ誣ゆべけんや。有唐の徳は、則ち朽ちざるのみ。十九日書す。(貞元元年正月五日、真卿は汝より蔡に移された。自分は李希烈のためにやがて殺されるであろうが、これは天命であって、いかんとも致しがたい。しかし善悪是非を明らかに見てをられる天の眼は、希烈といへども誣ひ欺くことができない。されば希烈は一時勢力を持ち得ても天下を得られるはずはなく、唐室の徳は深く民の心に徹してゐるから、亡びることはないのである。十九日書す。)」
さらに、希烈は、自ら帝位に就こうとして真卿に即位の礼儀を聞いてきましたが、真卿は、自分が覚えているのは諸侯が天子に朝覲するときの礼式ばかりで、謀反人が即位する礼儀など知らないと答え、度重なる脅迫にもついに屈しなかったので、結局、希烈は人を遣わせて真卿を殺させました。享年七十六歳。
以上が、巻の四に記された顔真卿の事績と遺言ですが、『遺言』では同巻の付録として、真卿と同時期に活躍した張巡の伝を掲げ、その遺烈を顕彰しております。後述するように、この張巡は我が国で、楠正成になぞらえられることが多く、忠義の問題を考える上で重要な人物であり、絅斎も巻の四における後半部分の大半を、この張巡の伝に割き、楠公との比較に説き及んでおります。
張巡について
張巡は、真源県(現在の河南省鹿邑県)の令(長官)をしておりました時、安禄山が反乱を起こし、上司にあたる譙郡(安徽省亳県)の太守、楊萬石は禄山に降伏して、張巡にも賊を迎えるように命じて来ました。これに反して、巡は、県下の吏民を率いて討賊の兵を挙げ、賊将令孤潮の本拠がある雍久を攻め、力戦してこれを退けました。ところが、潮がまた数万の兵を率いて城下に至ると、巡は門を開いて突進し、激戦すること六十余日、大小三百余戦に及びました。巡は潮と旧知の仲であり、城下で顔を合わし会話を交わすこと平日のようでありましたが、そのなかで潮が巡に「唐の天下は過去のものである。足下は、堅く城を守っているが、それは誰の為にしているのか」と問うたのに対して、巡は「足下は、平生、忠義を以て自ら任じているのに、今日の態度を見るにその忠義はどこに行ってしまったのか」と答えたので、潮は愧じてその場を退きました。
かくして潮の攻囲が久しくなる内に、朝廷の消息も不明となり、潮は巡に書状を送って降伏を勧告して来ました。そこで巡の部将六人は巡に建白して、兵勢は衆寡敵せず、もはやお上の存亡も不明になってしまった上は、降伏が最上の策であると上申してきました。これを巡は表向き許諾し、翌日、堂上に天子(玄宗)の肖像画を設置し、将士を率いて拝礼したので、一同感涙にむせびました。その上で、巡は、先に降伏を上申した六将を前に引き出し、大義を責めてこれを斬ったので、士気はいよいよ振るいました。絅斎は、張巡が孤立無援の状況下で主君の消息が不明となっても、抗戦を続けたことを重視し、『講義』のなかで「此のところ、大義の係る所、若し審にせずんば、忠義の士たりといえども、時によりて迷ふこと多かるべし。いかなれば人々戦をするも、皆我主の御為と思ひ力を尽すことなれば、もはや君已に亡びたりと聞くか、又は存亡を知れずと云ふ時は、力を落して、今は誰が為にか戦ふべきと思ひ、自ら可為(為す可き)やふもなきやふに思ひ、いかゞして便りをきかまほしく思ひ、已に君亡びたりと聞けば、誰が為にする軍でなければ、今は拒ぎても詮なし、左言うて只犬死を為さふえふも無しとて、敵より首尾よきやうに言ひをこせば、其を幸にして敵へ降り、主の亡ぶる迄は少しもいじらず守りつめて、主亡びて後は如此(此の如く)するからは、何のこともなく一分の言晴れは立つてはずかしきことも無く候よと合点するもの、古今挙げて不可数(数うべからず)。此大義を不知(知らざる)故也。長いこともない。我は天子の為に敵賊をうつ合点で軍を起したるからは、天子の御無事に御座あるは固より目出度事、好し天子に何事かありて亡びさせられたりとも、我目ざす処の敵があるからは、邪でも非でも、そいつを根から葉から討亡さざる間は、共に天地を戴かざる存念をすへたるは、張巡が志なり。それぢやによつて、首尾能く敵を亡したらば、何れにても我主の筋目の君をとり立て天下を渡すべし。それも無くんばそれなりにて可果(果つべし)。ちっとも都が亡びたほどに主が知れぬほどと云て、手前の戦をする義を見合せてすることはいらぬぞ。能く古今をならして見よ、能き大将は皆是ぞ。」と述べ、また強斎も『講義』のなかで「敵は大勢、味方は小勢、相手に成ることでも、張巡は何であれ天子の命で城を守りて居るからは、命なりに死する合点ぞ。楠正成金剛山を守られたとき、後醍醐天皇はとらはれ給ひて何と成らせられたやら知らねども、兎角此の城を天子の命で守るなれば、大義の根をすへて、遂に守りをヽせられた。見事なことぞ。」と述べています。
さても、賊の攻囲は数か月に及び、その兵勢は数万に達したのに対して、巡の軍勢はわずか千余に過ぎませんでしたが、巡は戦う度に勝ち、ついに屈しませんでした。そこで賊は寧陵を襲って巡の後方を遮断しようとしましたが、巡はついに寧陵を守って敵と対峙しました。その後、睢陽に転じて太守の許遠と共に賊と戦い、これを敗走せしめました。巡は戦いで得た牛馬などの戦利品をことごとく兵卒に分け与え、将士を激励したので彼らはよく奮戦しましたが、やがて賊の攻撃は激しさを加え、城中の糧食は尽き、米に茶紙や樹皮を混ぜて食う程の有様でした。このため士卒は消耗と飢餓に苦しみましたが、巡は機略を尽くして敵を撃破し、過酷な籠城戦が続きました。当時、近隣の諸将は、事態を傍観し巡の救援を引き受けませんでした。そこで巡はその将、南霽雲をして城の囲みを突破し、臨淮の賀蘭進明の下に派遣して救援を求めさせましたが、進明は、巡と遠の功績を嫉んで、これを承知せず、むしろ霽雲を饗応して引き留めようとしたので、霽雲は自ら帯ぶる刀で一指を断ち、使者の命を果たした印だと言って去りました。巡は遠と協議し、もし睢陽の城を捨て去れば、江淮全域を失うことになるとして、睢陽を堅守することに決しましたが、籠城軍の窮迫は極みに達し、兵士の多くが餓死していました。巡は、愛妾を殺して兵士に食わせ、茶紙も尽きたので馬を食い、それも尽きたので、雀や鼠を捕まえて食べ、それも尽きたので、兵士の鎧や弓を煮て食いました。もはや兵士は力尽き、戦うことができなくなったので、巡は天子のおられる西に向って再拝し、「死してまさに厲鬼(疫病神)となりて以て賊を殺すべし」と言い、ついに城は陥落して巡は霽雲と共に賊将、尹子奇に捕らわれました。
子奇は、巡に向い、「足下は、督戦するたびに、大声で叫び、まなじりは裂けて顔面血まみれになり、歯を噛んで皆砕けたと聞くが、どうしておめおめと生け捕られたのか」と聞くと、巡は「我が志は、逆賊を呑んだが、力が及ばなかっただけだ。」と答えたので、子奇は怒って刀で巡の口を抉り見たところ、たしかにわずかに三四本の歯を残すのみでした。さらに子奇は、霽雲を降伏させようとしましたが、巡は「南八(霽雲の呼び名)よ、男児たるもの死せんのみ、不義のために屈してはならぬ」と言うと、霽雲は笑って「できることなら生きのびて賊を皆殺しにしようと思いましたが、公はわたくしの心を御存じである、御一緒に死なずにおられましょうぞ」と言い、共に城に殉じました。
このように、唐室への忠義を貫いた顔氏と張巡、許遠、南霽雲等の生き様は後世に多大の影響を与え、後で見るように、文天祥は『正気歌』において「張睢陽(巡)が歯となり、顔常山(杲卿)が舌となり」と賦し、また謝紡得は、『初めて建寧に到りて賦する詩』のなかで「南八(霽雲)男児つひに屈せず。」と詠んでおります(後述)。
張巡の伝で重要なのは、絅斎が『講義』において、張巡を我が国の楠公こと楠正成に準え、独自の臣道論に説き及んでいる点にあります※。特に崎門学では、楠公を我が国の臣道を最も純粋に体現した忠臣として敬仰しており、絅斎から強斎に至る楠公観の変遷を辿ることは、崎門学の思想的展開と我が国臣道の蘊奥を理解する上で不可欠の議論と云えます。よって最後にこの点について論じます。
※張巡は、我が国において、楠公こと楠正成に準えられることが事が多く、それは例えば、三宅観瀾(絅斎門下であったが、水戸藩に仕えたことで破門された)が記したとされる『大日本史論贊』の「楠正成伝贊」においても、「楠正成の兵を用ふるは、機を決し勝を制し、孫呉に髣髴して、而も忠勇壮烈、殆ど唐の張巡と相似たるあり。巡は雍久を出で睢陽を守り、正成は赤坂を去りて千剣破に拠る。皆孤墉(孤城)に嬰りて賊の喉牙を鯁す。・・・寡を以て衆を撃ち、奇を出して窮りなし。・・・巡は城陥りて死す、正成は鑾輿(天子の輿)を奉迎し、首として推奨を蒙る。斯れ則ち異となす。湊川の戦に、正成、将に自殺せんとして、正季の、生に託して敵を滅ぼさんと欲するの語を聞き、笑を含みて地に入る。其の巡の、死に臨みて、厲鬼となり、以て賊を誓ふに視ふるに、又何ぞ相似たるや。此れ其の忠義の心、天地を窮め、万古に亘りて滅すべからず。身は死すと雖も、而も死せざるもの、固より自若たり。」とあり、また頼山陽の『日本外史』においても、「後の論者、或はこれを唐の張巡に比する者あり。巡は全盛の唐室を戴き、狂胡(安禄山)の偏師(副将、令孤潮、尹小奇)を拒ぐ。二顔、これが先をなすあり、許遠これが助をなすあり。而して江・淮を遮蔽し、城を守って死を致せるに過ぎず。公を以てこれを視ぶるに、勢の難易、功の大小、豈に日を同じうして語るべけんや。」とあるので判ります。この通り、『論贊』と『外史』は共に、張巡と楠公に共通点を認めつつも、その規模においては、雲泥の違いがあると述べております。
崎門における楠公論の展開
近藤啓吾先生によると、我が国における楠公に対する評価には毀誉褒貶があり、徳川光圀が「嗚呼楠公」の石碑を建立した当時に於いてすら、その専らの評価は、由井正雪の楠木流兵学に代表される様な、楠公を卓越した兵法家とするものか、桜井の別れ、湊川における壮烈な最期に示された忠節を称し、公を武将の典型、武士の鑑と見なす意見が大半であったと云います。(『四続紹宇文稿』所収、「楠公論の展開」)。これに対して、絅斎は『講義』のなかで、先に張巡が、主君の消息不明となった後も戦い続けた事と楠公の忠烈を比較し、公の偉大なる所以を次の様に説いております。いわく、「我が国にて楠正成が赤坂の合戦のときは、後醍醐天皇は已に笠置の軍に利あらずして、是を隠岐国へ遷し奉て、実に存亡の沙汰たしかに聞へず。それでも楠はわきひら見ずにかまわず戦ふ。此時に楠が心にも、天皇の御存命危きことは知て居れども、それぐるみにかまわぬぞ。・・・・・・正成が心には、設天皇此時若自然(死)のことありとも、かまう合点では無し。其かまわぬと云も、後醍醐天皇には心がないと云うことではない。惟其存亡ゆへに思ひちがへることはせぬ。天下の為にする軍で思ひ立つからは、どこまでも我命のあらん限りは独ぼうし(独りぼっち)になりても、赤坂の城で一僕使はずして朽果るとても、敵を滅ぼすまでは中々気散じに見合すことはせぬぞ。それが大義ぞ。」すなわち、主君たる後醍醐天皇の消息が不明になっても、賊を滅ぼすまで、死力の限りを尽くして戦ったことにこそ、その偉大なる所以を見出しているのです。ですから、千早城であれだけ奇策を駆使して戦い抜いた楠公が、その後、湊川の戦では、まだ逃げ落ちて再起を図る道もあったにもかかわらず、あっけなく自害し果てたことについては、その誠忠を確信しつつも、いまだ遺憾なしとしなかったのでした。それは、絅斎の学話を筆記した『箚録』に、「唐の張巡睢陽の戦に自害せざるも、後れたるに非ず、文山(文天祥)の執へらるヽまで戦ひたるも、主を思ひ宋を存したきの一念の忠義の実なり。近代武士の義の吟味は、只後れを取らざるの、名を汚さぬのと云までにて、つまるところは、小さき一分の意気づくよりさきなる事、大準に当てヽ云べきことなきは、皆此誤なり。楠などはけ様の名に拘り、意気までの人間にてはなけれども、公家衆は全体まヽくをふ(?)の様なる体にて、何事を云ても迚も用ひられず、高氏は西国を駆推催して来る、其禦ぐべき道をいへど、坊門宰相如きたわけを尽す故、最早生きて天子の御難儀になり給ふべきを見るに忍びず、総並に泥まぶして居られず、世の中、今は是迄と存じ切たる心、其の感慨、不忍の歎き、千載の忠義の人の涙をこぼすに勝ざる親切の忠臣なり。されば此世の中、今は是迄なりと思てと書る段こそ、記録の能く得たる。思とは詞に著はるヽ上の余詞なれば、楠が真言なるべし。(楠は武士の小さなプライドで死ぬような人物ではなかったが、高氏が東上してくるというのに、公家への諫言は容れられず、今はこれまでと観念した)此楠が忠義の心を不知者は、最早是ぎりにて、吾もよい死を取たがましと、あぐみ果て思棄たる様にとれば、大いに楠を知らずと云ふべし。惓々惻怛、忠能徹日月(忠よく日月を徹す)の心、誠に此一言にあり。扨又残念なるところも此一言にあり。此上ながら、七十騎にてもかけ抜け、いつまでも七代生れかはりても、朝敵を亡したきといふ詞の存念を遂げば、楠が材略にて大和河内に引込て、其時を俟ば、不成はいつ迄も天命勿論云に不及、何様の義も可為出事なり。此即屈原が宗国の亡るを見るに不忍して汨羅に身を沈められし心と事は替りて同日の談にして、忠にして過たると議せらるヽも此にあり。又千載の一人と称せらるヽも此にあり。嗚呼君臣の義の吟味不精しては、さて〳〵なりがたきこと、ケ様の事にて知るべし(わずかの軍勢での敵陣を突破し、河内に引き籠って時を待てば、何かできたかもしれない。これは屈原が汨羅に身投げしたのと同じで、忠に過ぎたものというべきである)。」とあるのでもわかります。すなわち、絅斎は、楠公の忠死は、小さな武士の一分ではなく、屈原が汨羅に身を投じたのと同じ、「惓々惻怛」の至誠に由るものとしながらも、まだ少しでも戦うことができたのに、いささか死に急いだ感があるのは「残念」にして「忠にして過ぎたる」ことであると評しているのです。
こうした絅斎の楠公観について、強斎は、彼の学話を弟子が筆録した『望楠所聞』において「楠の出処の正しきを知るべし。慇懃に万里小路藤房卿(後醍醐天皇の使者)を以て頼み思召と云勅定で出られた(勅諚による召しに応じた)。あれほどになふては、大義を引き受くることならぬ。軽々しきことでは、大義を引受くることならぬ。軽々しきことでは、大任の任にあたること難成(成り難し)。唯勿体を付て云ことでない。賢者の出処を見るべし。扨参内して段々申上らるヽ旨も、見たがよい。慥かな云分、何時でも私が身が存命で居るとさへ聞召さば、終には聖運を開かんと思召(せ)と。あの慥かに任じ切た云分、其より赤坂城に籠らるヽ様子、其後千破の城に籠りて居る内に、主上は隠岐に流されさせられたぞ。あそこで大体なものなれば胡乱ること、何を頼みにする軍と云ことじややら、あてどがない。其上加勢するものあらばなれども、誰加勢する者もない、楠唯一人、天下不残皆鎌倉方なるに、あの様に天下の兵を引受て合戦をすると云は、たヾでない。主上は流されさせられふとも、譬へ崩御なされふとも、一旦君に頼れて朝敵を征すると云が己が任に当りて、どこ迄も死して後止んと云様にあるからぞ。主上は流されさせらるヽと云ても、其時は社稷を重しとするの合点で、あのようにありたものぞ。太平記に楠が所存の程こそ不敵なれと云たは、能く書いたぞ。誠に纔の小城に僅かの小勢を以て天下を引受て戦ふと云は、右の所存でなふてはならぬこと。唯軍上手じやの謀計がよいのと云ことでないぞ。」(『望楠所聞』)と述べ、まずは楠公の孤忠を称えた絅斎の師説を継承しつつも、同時に絅斎が、楠公の死を「残念」、「忠に過ぎたり」としたことについては、「楠正成が湊川の討死は当らぬ、どこまでも性命を全ふしてこそなれ、討死しては当らぬ、正成だけじやと云たがるぞ。其程なことを合点せぬ楠ではないぞ。定てあそこに死なでならぬ其時の事体なるべし。どふもあとから論じられぬ。譬へあそこの死は当るにもせよ当らぬにもせよ、先づあれほどの忠義を立て、あれほどにして見たがよいぞ。どうした事体で死んだことやら知れもせぬことを、色々と云て、正成に疵付るはないことぞ。そふ体(総体)書を見るには、加様なことが大事ぞ。纔なことを揚げて色々と云んよりは、其人の惣体を推して見るようにしたがよいぞ。孔子の三都を討たせらるヽも、聖人に間然せふことはない筈ぞ。然るに三都を討つとて、負て帰らるヽ、不調法に見ゆる。圍之不克と云てある。何ともどふも済まぬことぞ。聖人の軍に軽々しきこともない筈。負て帰るなど云やうなことはありそむないものなるに、あの様な事体、どふしたことやら知れぬことぞ。楠も出処から見ても、何から見ても残る所ない、間然ない楠ぞ。其にあの様にあることは、定てあのやうになふてはならぬ事体ありと見へたぞ。書を見るに、此心得、第一ぞ。」と述べ、師説を斥けております。
近藤先生によると、絅斎の師説を厳格に継承した筈の強斎が、こうした楠公の出処に関して相違する見解を示した背景には、上述した『望楠所聞』が筆記されたと思われる享保十年から十一年に先立つ一定の期間において、彼が最も神道の修養に力を致したことによる思想深化が大きく影響しているとのことです。すなわち、享保八年に高宮を訪うて多賀社に詣で、高宮で『日本書紀』神代巻を講じ、また翌九年には闇斎の霊を祀る垂加霊社を多賀社祀官の邸内に勧請、同年春には門人山口春水の仲介で祇園社祀官の山本主馬より闇斎伝来の神書の附属を得、「守中」の霊社号を受け、『風水草』を書写するなど、急速な勢いで神道を習得しています。さらに、望楠軒の名の由来ともなった、楠公の「仮にも君を怨み奉るの心発らば、天照大神の御名を唱ふべし」という言葉を山本主馬から聞いたのもこの年です。こうした、神道修養の結果、強斎は、天照大神を根源とし、祖先から子孫に連なる生命の自覚に至ったのであり、その思想的境地に拠る強斎の楠公観は、彼の学話を録した『乙巳録』において、「楠は唯々軍上手の武勇なのと云ふが、さうばかりでない。男たる者は、あそこの存念が望むところ。あの様に一点うらみなし君に向ひ切つた人は見ぬ。既に死にざまも、生きかはり死にかはり、朝敵高氏を亡ぼさんと」とあることに示され、楠公が、弟正季と「七生賊滅」を誓って刺し違えたのも、「いまの世、人々すべて高氏といつてよく、されば一高氏を滅ぼし得たとしても、それに続く高氏は、なほ次々に現はれることであり、これを滅すことは、我が一代の力をもつてすること不可能であれば、我れ先づ戦場に斃れて志を留め、後人の我が骸を乗り越えて後に続く諸高氏を打滅ぼしてもらひたい、といふものであつて、これ、我が一死をもつて後人の奮起を期せんとしたものであり、強斎のいふ「既ニ死ニザマモ、生キカハリ死ニカハリ、朝敵高氏ヲ亡ボサント」は、そのことをいつたものに外ならない。」(近藤先生『四続紹宇文稿』)のです。周知の様に、楠公は、九州から東上する高氏の大軍を平地で迎え撃つのは不利とし、朝廷に一旦、比叡山に遷御することを諫奏しましたが、公卿らの反対で容れられませんでした。しかし、一度出陣の君命が下るや、胸中一点君を怨み奉る心なく、従容湊川の死路に赴いたのでした。このとき楠公の心を貫いたものは、まさしく『拘幽操』が説く「真実君がいとしうて忍びられぬ至誠惻怛の本心」に他ならず、楠公は、天照大神の御名を唱えることによって、自らの生命の本源に回帰し、あえて君命に死することによって、生き変わり死に変わりして、賊を滅ぼそうとしたのです。
この神道的境地に立つ楠公観への深化は、強斎が、闇斎と絅斎の義絶によって崎門と垂加に分裂した闇斎学を再び合一し、崎門学の正統を「望楠学派」として確立する過程と相即するものと云えます。
以上、顔真卿から説き起こし、張巡を介して、崎門学における楠公論の展開を見て来ました。顔真卿や張巡が、主君の消息不明となっても孤忠を貫いたことは、「士は己を知る者のために死す」といったシナ式の忠義や、「御恩と奉公」の関係でなり立つ封建的な主従関係とは全くかけ離れたものです。また、君命に逆らう訳にはいかないと言って、汝州に赴いた顔真卿の態度は、従容湊川に赴いた楠公の態度とも通じます。絅斎は、楠公を張巡の孤忠になぞらえることによって、従来の単なる優れた謀将、武士の鑑とする評価を脱却しましたが、いまだそれは朱子学の影響下に止まるものでした。これに対して、強斎は、神道的修養を積み、生命の祖孫一貫一体の自覚に立つことによって、楠公の忠義をより蘊奥において理解し得たのであり、それは取りも直さず、我が国臣道の精華を発明すること他なりませんでした。