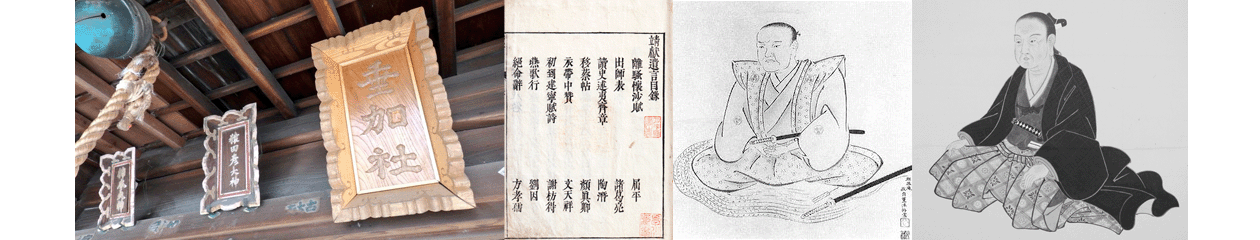文天祥の主君である徳祐帝は皇位の御印である国璽を元に奉じて降伏し、自らも皇后や太皇太后と共に北送されてしまいました。しかし、国璽を敵方に奉じるということは、事実上の退位を意味するものであり、文天祥はそのことを大義名分にして二王(端宗と衛王)を新帝に奉じて元への抗戦を続けたのでした。次に第七巻の主人公である謝枋得も文天祥と同時代の人物であり、そこで扱う主題も天子が夷狄に降伏してしまった場合、遺された臣民は如何に身を処すべきかという問題に変わりはありませんが、本巻では特に、最早夷狄の籠中にある天子が発する詔命が、はたして天子の命として正当かどうかという点が問題になります。
謝枋得は字を君直といい、南宋の宝慶二(一二二六)年、信州は現在の江西省上饒県の出身です。寶祐四年、枋得三十一歳の時に礼部(我が国でいう文部省)で行われた省試を受験して首席で及第し、皇帝自ら出題する殿試に臨みましたが、時の大臣宦官を罵ったため、第一甲から第五甲まである合格者の内、第二甲の首席に止まりました。ちなみにこのときの第一甲の首席が文天祥であり、合格者のなかには前巻で出て来た陸秀夫などもおります。
その後、枋得は帰郷した翌年の宝慶五年、江東・江西両方面の宣撫使であった趙葵に召されて礼部・兵部両部の架閣に任ぜられ、信州・撫州両地方の義士数千人を召集して元軍の来寇に備えました。ここでいう宣撫使とは天子の旨を宣べて民衆を撫安する職で、枋得が任じられた両部の架閣とは官庁の帳籍文案を管掌する官名です。
ときに、中央で権勢を振るっていた大臣の賈似道は、功のある人物が己に代わらんことを忌み、当時の将軍たちを失脚させようと、会計官を前線の各軍に派遣して収支を調査させました。その狙いは、「なにとぞ大将どものおちどを見出さぬと思へども何にもないゆえ思ついて兵糧のぎんみ(吟味)によこめをまわす。兵糧と云ものは何が大勢して食ふもの。はたらくときはてんでんに食うぞ。又さわがしきときは盗をするで有ふ。なにときこれがいりめ(入目)のつもられぬものぞ。それを知てさんよう(算用)せよと云。」(絅斎『講説』)とあるように、兵糧と云う軍会計の弱点を突いて落ち度を暴き、失脚に追い込もうという策略です。やがて賈似道の使者が信州に至ると、枋得は宣撫使を庇おうと、家財を売り払って収支の不足を補ったために官を奪われました。
景定五年、枋得三十九歳の時、彼は科挙の試験官を命じられましたが、試験問題のなかで賈似道の姦悪を暴きあげ、言を極めてその罪を弾劾したため、またしても官を奪われて興国軍(湖北省陽新県)に追放されました。枋得は、宋室の命運が二十年後に尽きることを確信し、宋を何としても亡ぼしてはならないという一念から賈似道と抗論し、失脚しても節を曲げませんでした。興国軍では、疊山と号して山門に籠り、一人道義を考究しておりましたが、人々はその理に対して厳格で、孤高を貫く態度を慕い、その土地の長官以下多くの民衆が彼に弟子入りして物事の理非曲直を尋ねたと言います。そんな枋得が座右の銘とした「清明正大の気、利を以て回すべからず、英華果鋭の気、威を以て奪ふべからず(清明正大の気は利益で釣っても、もとへ回すことができず、英華果鋭の気は権威をもっておどしても、かへさせることができぬ)」という言葉は、彼の面目を良く表しております。
南宋の滅亡とその後
徳祐元年、枋得は五十歳にして江西の招諭使、次いで信州知事に任ぜられました。招諭使とは「降参する者を此方へ招き、叛く者を諭して、総体の司さになる役」(強斎『講義』)のことで、一種の軍司令官です。折しも元軍は長江流域に来寇したため、枋得はこれを安仁で迎え戦いましたが敗れ、妻子みな捕らえられ、自身は老母を奉じて建寧山中に隠れました。彼は山中で賤者に身をやつし、宋の滅亡を知ってからは、毎日喪服を着、都臨安の方を向いて慟哭したため、理由を知らない人々はこれを見て病人であると思いました。後に建寧を去って建陽に移り、さらには閩中(福建省閩侯県)に至りました。
それから時はたち、元の至元二十三年、枋得六十一歳の時、元主フビライは、臣下の程文海を江南に遣わして人材を求めさせたところ、文海は宋の遺臣三十人を推薦し、その筆頭に枋得の名を挙げました。しかしこれを聞いた枋得は、文海に手紙を送り、「自分が、宋が滅んだにもかかわらず死ななかったのは、九十三歳の老母が居たからだ。しかしその母も去年二月に死んだので、もはやこの世に何の関心もない。亡国の大夫でいやしくも義理を識る者は、自らの存立を図るべきではない。」といって、その推挙を断りました。そこで、元の時代、地方を統括する為各地に置かれた行省の大臣をしていた忙兀台は枋得を招待し、手をとってその浪人暮らしを労い、仕官させようとしましたが、これにも「枋得の名は亡国の臣のことであるから不吉である」と言って断りました。そこで次に、宋から元に逃れた大臣の留夢炎が、仕官を力説しましたが応じませんでした。
これを見た福建省の大臣である魏天祐は枋得を説得して自らの功績にしようと企み、彼を欺いて自らの城に召し入れ、説得を試みましたが、枋得は天祐を相手とせず、かえって傲岸無礼な態度をとったため、天祐は怒り、「汝は天子より地方の長官を拝し、国境の守備を命じられていたのに、安仁に戦いに敗れても死ななかったのは何故か」と言って枋得を責めました。すると枋得は、「程嬰や公孫杵臼の故事」(『史記』に晋の臣屠岸賈、その君趙朔を殺し、趙氏の遺児も殺そうとしたが、趙氏の客友である程嬰と公孫杵臼が相謀り、程嬰は趙氏の遺児を匿い、杵臼は他人の児を趙氏の児と偽って殺された。それから十五年、晋の景公、屠岸賈を滅ぼすに至って趙氏の遺児と程嬰を召したが、程嬰は事成れりとして自殺した)を引き合いに出し、龔勝が餓死したのは王莽が漢から帝位を簒奪してから十四年後のことであるがそれでも忠臣の名は失っていない。韓愈が「棺を蓋ひて事始めて定まる」と言い、司馬遷が「死は泰山よりも重く、鴻毛よりも軽きことあり」と言ったように、人の真価は死ぬまで分らないのだと云って反論しました。天祐はこれを詭弁だと言って難じましたが、枋得も足下には何を言っても無駄だと言い返したので、結局天祐は怒って枋得を大都に北送しました。この北送に当り、枋得が死を誓い、門人・故友への訣別の辞として賦したのが、絅斎が枋得の遺言とした『初めて建寧に到りて賦する詩』です。以下に本文を掲げます。
『初めて建寧に到りて賦する詩』
雪中松柏いよいよ青青。綱常(※1)を扶植する此の行にあり。
天下久しく龔勝(※2)が潔あり。人間なんぞ独り伯夷のみ清からん。
義高くして便ち覚る生捨つるに堪ふるを。禮重くして方に知る死甚だ軽きを。
南八(※3)男兒つひに屈せず。皇天上帝眼分明。
※1綱常は三綱五常
※2龔勝は、前漢の纂臣王莽に抗して死んだ人物
※3南八は南霽雲で、安禄山と戦った唐の武将です。
併せて以下に強斎の『講義』を掲げます。
「「雪中云々」とは、孔子の「歳寒くして然る後、松柏の凋むに後るることを知るなり」と仰せられたから云はれたぞ。「愈々」とあるが別して孔子の餘意まで発せられたぞ。孔子の松柏凋むに後るると仰せられたが、雪中でもみさほ(操)をかへず、愈々青々として見へる。節義を守る者は、常から人には越えて見えるものじやが、乱世でいよいよ忠義のほどが見える。三綱五常の大節義をたすけ立つるは、此の度のことじや。ええさて久しう龔勝の様な忠義ななかまが無うてさびしかつたが、されども拙者が居るからは、何の伯夷ばかりが清からうずとあること。忠義のなりを任じた語意ぞ。前の「綱常を扶植する此の行に在り」と云はれた気象は、ここで見えるぞ。「義高くして便ち覚る生捨つるに堪ふるを。」義のなりにかへらず、義なりに高い場になつては、命ほど大事なものはなけれども、何とも思われぬ、惜しい気はないとあることぞ。「禮重くして方に知る死甚だ軽きを。」子としては孝、臣としては忠と云ふなりに身を尽すが礼、其の礼なりにかへう様もなく大事な時に至りては、死はものの数とも思はれぬ。礼にくらべてみれば甚だ軽いことじやとあること。「南八男兒つひに屈せず。皇天上帝眼分明。」南霽雲忠義な者で、遂に節義なりに身を屈せず死した。天道の能く見すかしてござるではないか、とあること。」
北送の途中、枋得は餓死せんとしてほとんど食べ物を口にせず、次第に体力衰弱して病を発しました。そして元都に着くと、謝太后の仮の墓所と徳祐帝の在ます所を訪れて再拝慟哭し、病状悪化するなかで医者の治療をも拒み、終に死にました。享年六十三歳。枋得の死後、息子の定之が枋得の遺骸を郷里の信州に埋葬しました。この定之もまた父の志を継いで元に仕えませんでした。また枋得の妻の李氏は、元の将軍が妻にしようとしたのを拒み、自ら首を括って死にました。この他、枋得の弟や叔父とその妻子なども皆元に屈せず、節義に死んだことでありました。
「みづから臣たるの義を尽くす」
以上が『靖献遺言』が記す枋得の事績ですが、重要なのは枋得が、前述した留夢炎に与えた書である『劉忠斎に遺る書』のなかで、自らが元の招聘に応じない理由の一つとして、太皇太后から降伏を命ずる詔書をいくたびも頂きながら、全て返事をせず、そのまま太后が崩じて久しくなるいまとなっては、粗飯を供えて太后の御陵にお参りする面目もないことを挙げていることです。徳祐帝の母君である太皇太后は、枋得の再三の諌奏にもかかわらず、二三の大臣の謀を信じて祖宗の土地人民を悉く元に献上し、自らも徳祐帝と皇后と共に投降して大都に北送されてしまいました。そして大都から枋得のもとに書状を下し、元に降伏するならば、宋の宗廟社稷を残し民衆を救う事ができるといって降伏を命じましたが、これは三歳の童子から見ても、元が群臣たちを欺き、降伏させるための方便であることは明らかでした。これに対して枋得は「宗社存すべからず、生霊救ふべからざるを知り、太母に従ひて以て帰附せず、此れ某の人臣たる、みづから臣たるの義を尽くすなり。(宗廟社稷は残すことはできぬ、民衆は救うことができぬ、そして太后に従って降参することもできぬといふことは、わたくしが宋の臣としてみづから臣としての道義を尽くすといふものである。)」と記し、また「君臣は義を以て合ふものなり。合へば則ち就き、合はざれば則ち去る。(君臣は道義をもって相合ふものであって、合ふときにはつかへ、合わぬ時には去るべきである。)」と記して、太后の詔命に従いませんでした。
こうした枋得の態度は、まさに文天祥が「社稷を重しとし、君を軽しとなす」と言った態度と通底し、絅斎も本巻において、明の学者である許浩の「嗚呼、精忠勁節、文山前に倡え、疊山(枋得)後に継ぐ。その行う所を質すに、一轍に出づるが如く、綱常を夷狄華を乱すの時に扶け、風化を宋祚傾頽の際に振ふ。身死すと雖ども、いまに至りて英気凛凛として猶ほ存す。身を殺して仁を成し、生を舍てて義を取る。二公能く孔・孟の訓に遵ふと謂ふべし。」という言を掲げています。
文天祥との違い
もっとも、文天祥と枋得に共通する点が多い一方で、両者の間には微妙ではありますが本質的な違いがあります。天祥の場合、徳祐帝は国璽を元に奉じてしまったのであり、それは事実上の退位を意味しました。ですから天祥はそのことを大義名分にして二王を新帝に戴き元との抗戦を続けたのでした。また絅斎と強斎の『講義』ないしは『講説』でも見たように、彼らが後醍醐帝に従って高氏に降った瓜生判官を批判したのは、既に三種の神器が一宮(恒良親王)に渡され御位が譲られていたにも関わらず、瓜生判官が後醍醐帝の綸旨を本物と信じて降伏したからでした。しかし枋得の場合、彼は降伏を促す太皇太后の命が本物であることを知りながらあえてそれに従わず、抗戦を続けたのです。太皇太后は皇帝ではないので、その命は君命ではありませんが、絅斎と強斎は共に、それがたとえ本物の君命であったとしても従う必要はないと述べているのです。強斎は先に枋得が記した「みづから臣たるの義を尽くす」の意味について、「君はどうあれ某は宋の臣たるなりに義を守るとあること。かふした大義を知らぬに依て前に云た様に瓜生判官が高氏にたらされた。たとひ本(本物)の勅にしてからが高氏が様な賊と和睦なされたらば賊と一つになられたと云もの。すれば何ほど勅じやと云ても従ふ筈がない。どうなりともして天照大神以来の皇統を正ふ立るが全体の忠義ぞ。」(『講義』)と述べ、また絅斎も「もはやこのときは社稷にあずかる戦ひなれば社稷が重ひゆえ降参する君なれば社稷から云へばかたき(敵)ゆへ、ゆだんしらるると大后からしてあぶないめにあわするがどれもくらい。義貞が北国へをちるとき瓜生判官がみやこがたなるに尊氏が似せ編旨をかきて天王は降参なされてあれは朝敵なり天子の勅なるほどに尊氏にそくいして義貞を討べしと云ふれる。瓜生がこれをまんまことにしてだまされたと云うて今で笑ふ。これがもとまぐれものゆへなり。天王の胤として尊氏に降参なさるるよふな天子で天照大神以来の正統を失ひ玉ふような君なればもはや正統のたたかひゆへこのみやこ(宮子)をとりたて奉て天子の位にそなへてたたかわす。一度天子の位にござればらうぜきなことはなるまい故おしこめ奉てもくるしくなし。義貞は朝敵などと云せてある編旨ならばにせは云に及ばずたとひ天子の勅筆であそばすとも引さいてすててとがはないことぞ。それを天子の降参なされたとてきもつぶして降するは、だだいかどのまくれた勇ぞ。正成などはこの筋がみえたそうな故天子のながさせたまふをききてもはや千破屋城を守りてぎくともせぬ。天子がなければ君をとりたてる人がなければつれひとりきりしぬ合点なり。」(『講説』)と述べております。
以上で述べられているのは、次のようなことでしょうか。すなわち、後醍醐天皇が高氏に降ったのは偽の三種の神器を擁されてのことであったから、正統は一宮であり、高氏への降伏を命じる綸旨は無効である。しかしたとえ後醍醐天皇の擁し給う神器が本物であり、依然天皇が正統にましましても、敵である高氏への降伏を命じる綸旨は無効である。これは君命に対する絶対服従を説くこれまでの主張と矛盾するようにも思えますが、どういうことでしょうか。おそらく、絅斎にとって君命は絶対であるが、例外があります。それは、天子が乱臣や外敵に降伏して国璽(我が国の場合、三種の神器)を渡してしまう場合です。何故ならば、その場合、国家の正統は覆り、三綱五常や君臣内外の分別といった、国家存立の根本をなす道義が紊乱し、やがては国家の衰滅をもたらすからです。
宋金交渉始末
したがって、正統なる天子を戴く国家が、どんなことがあっても外敵に降伏してはならないのは、それによって領土が奪われ人民が危害を受けるからではなく、国家の道義が頽廃するからです。絅斎は、枋得の巻の大半を宋と金の交渉に関する記述に費やし、目先の平和を目的とした講和の名による降伏が、いかに甚大な災厄を国家にもたらすか、様々な資料を掲げて論証しておりますが、なかでも、南宋の時代を生きた朱子が、紹興三十二年に孝宗の求めに応じて奉じた『壬午応詔封事』には重要なことが書かれています。この『封事』のなで、朱子は、およそ世間で和戦の得失を論じるのに、主戦派と講和派がそれぞれの長所を飾って議論が一定しないのは、彼らが何れも利害の末節に走って義理の根本を見ないからであると述べた上で、「仁は父子より大なるなく、義は君臣より大なるなし。是れを三綱の要・五常の本と謂ふ。・・・その君父の讎、與に天を戴かずといふものは、乃ち天の覆ふ所、地の載する所、凡そ君臣・父子の性あるもの、至痛みづから已むあたはざるの同情に発して、専ら一己の私に出づるにあらざるなり。国家の北虜(モンゴル人)と、乃ち陵廟の深讎、その與に天を戴くべからざること明らかなり。然らば則ち今日まさにすべき所のもの、戦ひにあらざれば以て讎を復することなく、守りにあらざれば以て勝ちを制することなし」と述べ、「君父の讎は共に天を戴かず」という義理の根本から金との講和に反対し、あくまで徹底抗戦を主張しています。これはどういうことかと言いますと、先に、北宋第八代皇帝である徽宗の時代に華北の領有をめぐって金と不和が生じ、金が宋に侵攻してきた際、金の猛攻に恐れをなした徽宗は欽宗に譲位して出奔し、やがて宋の都も金軍に包囲されてしまいました。これに対し李綱等の忠臣は徹底抗戦を主張しましたが、金は莫大な賠償金と領土の割譲、金帝を尊んで宋帝の「伯父」とすることなどを条件とした和議案で欽宗を眩惑したため、欽宗は李綱を罷免し、自ら先帝である徽宗と金軍に投降してしまいました。すると金は欽宗から皇位を剥奪して庶民の身分に落とし、二帝および后妃・太子・宗戚三千人を拉致して北に去りました。これが欽宗の年号に因んで「靖康の変」と呼ばれる大事件であり、この事件を以て太祖趙匡胤以来百六十年続いた北宋は滅亡したのでした。
しかしその後、欽宗の皇子でありながら、唯一北去を免れた皇子である康王が即位して南宋の初代皇帝高宗となります。高宗は前出した李綱を召して夷狄討伐を誓いましたが、またしても黄潜善や汪伯彦らによる和議工作に阻まれ、さらには高宗が講和派の元凶である秦檜を信任すると、秦檜は岳飛や韓世忠等の主戦派を斥けて金と和議を結び、その結果、宋は金に臣下の礼を取り、毎年莫大な歳幣を朝貢することになったのでした。この高宗の後を継いだのが、朱子が『封事』を奉った孝宗であり、朱子が『封事』のなかで金を「君父の讎」と言ったのは、「靖献の変」で、徽宗・欽宗の両帝が金によって拉致北送されたことによります。
かくして成立した宋金の和約は南宋に一時の平和をもたらし、南宋は農業生産の向上や運輸交通の発達によって空前の経済的繁栄を謳歌しましたが、所詮それは夷狄である金に中原を奪われ臣従を余儀なくされた「敗北の平和」に過ぎず、やがては元の勃興と侵略によって南宋もまた滅んだのでした。南宋滅亡の顛末は、文天祥のくだりで見たとおりです。
さて、これまで謝枋得の巻を見てきましたが、翻って戦後の我が国の歴史に目を転じれば、いささか慚愧の念に堪えません。というのも、先の大戦の結果、我が国はポツダム宣言を受諾し、アメリカに降伏しましたが、この降伏は、「国体を護持しうる」という条件の下でなされたものであり、三種の神器はアメリカに奪われておりませんし、いわんや天子が敵国に連れ去られるといった悲劇もありませんでした。したがって宋とは違い、国家の正統はかろうじて維持されておりますが、一方で戦後GHQが作成した現行憲法は国民主権を定め、米軍は依然として我が国への駐留を続け、我が国政府は毎年数千億円もの歳幣をアメリカに朝貢しています。たしかにそれによって戦後の我が国は空前の物質的繁栄を謳歌しましたが、それも所詮は南宋と同じく一時の「敗北の平和」に過ぎず、国家の道義は頽廃し、元国ならぬシナ中共の軍事的台頭によって、虚構の繁栄は打ち砕かれようとしております。このように、絅斎が記した宋金交渉始末は、現在の我が国にとって切実な教訓を示しています。